後藤氏、無念。
- mahomiyata45
- 2015年2月1日
- 読了時間: 4分
今朝、起きると、携帯ニュースに「イスラム国、後藤さん殺害」の文字が。人質となってから1週間以上が経過し、一部では解放に対する期待の声も聞かれた。しかし、やはりISIL。
ヨルダン政府や国民の事情を考えても、今回の結果は悔しいが、精一杯の結果だったのではないだろうか。
しかし、私たちは悲しむばかりではならないだろう。最も再考しなければならないのは、二度と同じことが繰り返されないために、犯行防止を考えること、そして、今回の政府の行動を良くも悪くも反省することなのではないだろうか。
例えば、日本政府は、2か月も前に、ISILによる湯川氏、そして後藤氏の拘束を確認している。しかし、彼らが人質となる前に、ISILに直接(外交チャンネルがないと言っても)解放を働きかけるようなことがあったとは言えない。人質となり初めて「人命第一」と声明したが、そもそも、攻撃をされたわけでもないISILに対し、「敵」と見なされても仕方ないような、有志連合(アメリカなどのISILに対する反戦国家)への協力的態度、発言、訪問などを繰り返した。人質となる可能性が十分にもあったにも関わらず、どのような意図で、ここまで行き過ぎたパフォーマンスをしなければならなかったのか。米軍基地問題や、TPP、日米安保条約による国土保護など、アメリカに対して、外交がデリケートにならざるを得ない状況は否めないが、今回の日本政府のパフォーマンスが行き過ぎたことは言うまでもない。
一方、ヨルダン政府は、ISILの敵国である。彼らは、アメリカと同様に、奇襲戦をしかけ、たまたま墜落したパイロットが捕虜となったのだ。彼は確かに自らISILの占領地域へ潜入したわけではない。しかし、事情が異なるにしろ、ヨルダン政府は、彼が捕虜となった瞬間にISILと交渉し、その際に、サジダ・リシャウィ死刑囚との交換を提案されていた。
しかし、ヨルダンも先述の通り、アメリカと同じ、有志連合。世論ももちろんのこと、彼らがテロリストと交渉することは、気の引けることであった。そして、今回の日本人人質事件が発生する。
ここまででも、日本政府とヨルダン政府の人質、捕虜に対する姿勢。そして、「事」の発生から行動に移すまでの時間差がよくお分かり頂けると思う。
ヨルダンは、ISILの占領地からかなり距離的にも近く、宗派の差などはあっても同じイスラム教(ISILに関してはそう名乗っているというべきかもしれない)である。ISILに対する知識量が全くことなったということも現状だが、今回の事件をしっかりと胸に刻み、実質的、文化的な距離に関わらず、全世界に目を向けるべきであるということがよくわかったのではなかろうか。
また、ヨルダンは、今回の交渉に関して、ヨルダンは、パイロットの生存確認を第一にしていた。ISILが、湯川氏の殺害報告から後のメッセージを全て画像に音声をつけるなど、動画としなかった点からも、後藤氏に関しても、いつまで命があったのか怪しい。パイロットも同じである。後藤氏の生存に関しても確認できていたかどうかといえば、できていない。全てISILのパフォーマンスであった可能性も否めない。
このような状態で、日本政府が、ヨルダンに対して、極悪犯を交換しろというのが如何に、無理な要求であったかもわかるだろう。
日本政府も、このように、交渉するにしても、その経緯があまりにも不慣れである。万一、ヨルダンが死刑囚を日本のために差し出すと決意し、それがなされたのちに、生存していなかったとなれば、日本政府はどのように責任を取るつもりであったのか。
そして最大の問題点は、我々は有志連合ではないにも関わらず、テロリストと交渉しないということに署名している。もちろん、テロリストとは、いかなる理由があっても交渉しないことが望ましいのは言うまでもない。それが金銭であれば、武器や戦闘に使用される可能性も高く、また他の用途だとしても、彼らテロリストに対する支援になることに他ならないからだ。また、今回のように、極悪犯との取引も現にある。彼らを解放した時に、その後テロや殺戮があれば、その被害者の命へどう我々は責任が取れるというのか。しかし、ヨルダンを挟んででも、今回のサジダ・リシャウィとの交換が成立していれば、それは、何を意味したのか。国民の命も守らなければならない政府であるが、他の国の市民たちの命をないがしろにしていいわけがない。
今回のような、宗教戦争に関して、(ISILがムスリムかどうかは議論の余地はあるが)やはり、我々は部外者でしかない。そしてその部外者ができることは、どちらかの立場に立つのではなく、真相を知り、そしてそれを見守るしかないのではないか。
自身らのアジアとの関係などを考えてもよくわかるだろう。宗教も含め、歴史というのは、奥深く、真相はわかり得ない部分も多い。そんな中で、何もわからぬ部外者は無関心でもならないし、深く関わってもならないのではないか。
一番大切なことは、当事者が、現状を受け容れ、歩み寄ることを考えることなのだと思う。
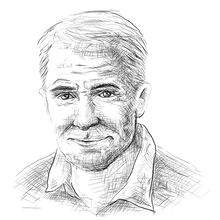



Kommentare